
元旦礼拝


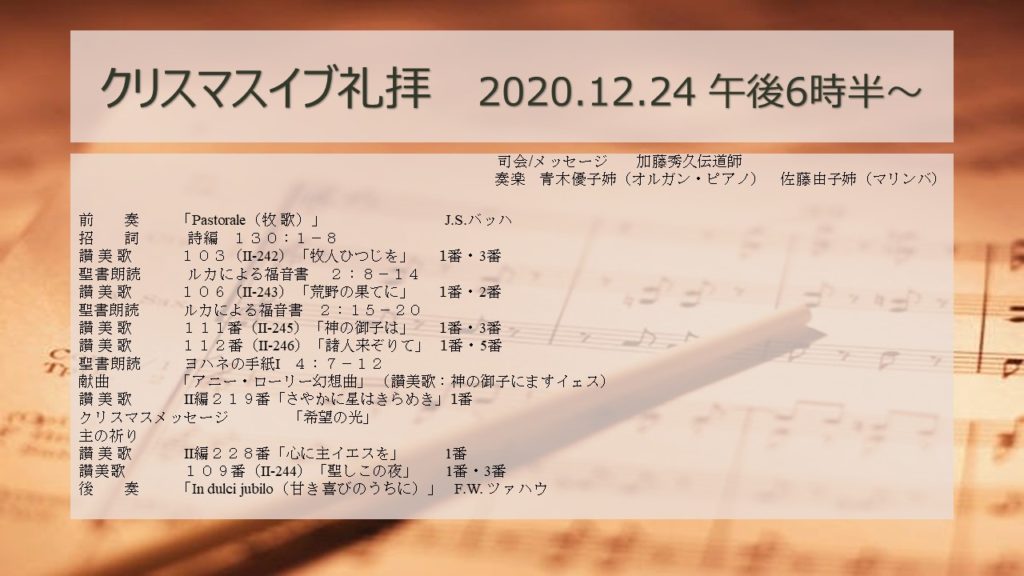
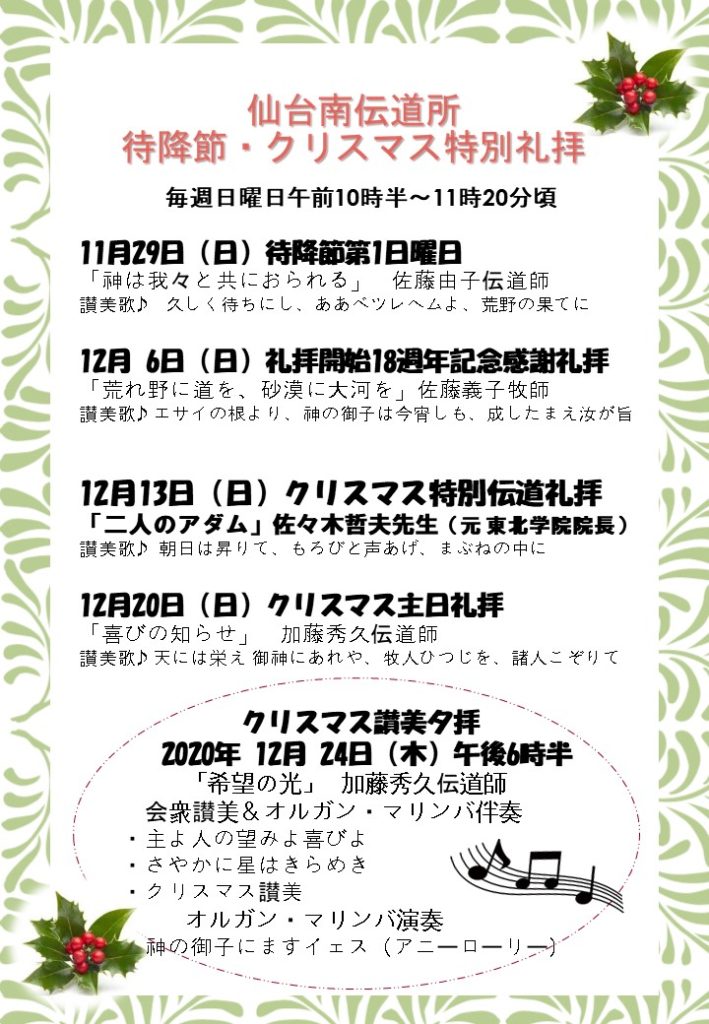
★礼拝堂/集会室は暖房をつけていますが、換気の為、窓を開けている状態で礼拝を行っています。どうぞ暖かい服装でお越し下さい。
エゼキエル書 36:25-28・ヨハネ福音書 14:15-26
「現臨する神様を伝える『真理の霊』」 佐藤 義子牧師
*はじめに
今日は、ペンテコステの記念の礼拝です。社会ではクリスマスとイースターに比べてペンテコステはほとんど知られていません。ペンテコステはギリシャ語であり、日本語で「聖霊降臨日」と呼んでいた方が、もう少し広まったようにも思われます。しかし「聖霊降臨日」と聞いても、日常的な用語ではないことに加えて、イエス様は聖霊について次のように語られました。「この方は、真理の霊である。世は、この霊を見ようとも知ろうともしないので、受け入れることができない。」(17節)
*「世は・・・受け入れることができない。」
2000年以上も前に、イエス様が聖霊降臨の予告をされた時に、「この世では、真理の霊(聖霊)を見ようとも知ろうともしないので受け入れることが出来ない。」と、すでに言われていたことに注目したいと思います。
私達は、この世・この世界で、<限られた時間と空間>の世界を生きています。それゆえ多くの人達は、<時間と空間の世界を突き抜けて>天から聖霊が降るという出来事は日常を越えており、関心を持たずに受け入れられない、ということでありましょう。人は何かを見たい、知りたいと思えば、それを実現する為の道を考え実行します。けれども見ようとも知ろうとも思わなければ、どんなにそのものに価値があっても、それに触れることはなく、見ても、聞いても、ただ素通りで終ってしまうことでしょう。
*「しかし、あなたがたはこの霊を知っている。」
「あなたがた」とは、イエス様とまもなく地上の別れを迎える弟子達であり、そして今は、弟子達の信仰を継承している教会の私達クリスチャンのことです。そうです!私達クリスチャンは、世に属さず、聖霊を知っているのです。その証拠に、以下のみ言葉(コリント書12:3)があります。
「聖霊によらなければ、誰も『イエスは主である』とは言えないのです。」
バプテスマを受けたすべての方々は、イエス様を「神の御子・救い主」と信じて信仰の告白をしました。この信仰は自分の力で信じたように思われがちですが、そうではなく、聖霊によって確信が与えられ、告白に導かれたことを、聖書は私達に教えています。
*「わたしは、あなたがたをみなしごにはしておかない」(18節)
イエス様が地上を去られた後、弟子達は、罪のないイエス様を罪ある者として殺してしまう、この世の勢力に、押しつぶされてしまうのではないでしょうか。実際、復活のイエス様が弟子達の所に来られた時も、弟子達はこの世の権力を恐れて戸には鍵をかけていました。イエス様は弟子達の弱さをご存じでした。それでもなお、この地上に神の国を打ち立てていくためには、イエス様が地上を去った後もこれまで通り、神の国の福音は宣べ伝え続けられていかなければならず、この世の終りが来る迄に、一人でも多くの人達が救われることが神様の御心・御計画であるゆえに、弟子達には(そして勿論私達にも)「助け手」が必要でした。
*「わたしは父にお願いしよう。父は別の弁護者を遣わして、永遠にあなたがたと一緒にいるようにしてくださる。」(16節)
「弁護者」と訳された原語には以下の意味があります。「助ける為にそばへ呼び寄せられた者、支持、弁護する為にそばに呼ばれて来ている者、肩を持ってくれる人、被告の友人で彼の性質について弁明し、同情を持って味方してくれる人、助け主‥等」。(後見人(後ろだて)」と訳す注解書もある。)イエス様は、「弁護者、すなわち聖霊が、あなた方にすべてのことを教え、わたしが話したことをことごとく思い起こさせてくださる。」(26節)「この方は真理の霊である」(16節)とも言われました。
*私達の伝道
「聖霊・真理の霊」は、私達の心の内に真理を浸透させて下さいます。私達が真理の霊によって呼び起こされる時、私達の心に「真理」が支配し、それにより私達は罪や堕落から守られます。私達クリスチャンが、与えられた場所で、イエス様の教えを思い起こしつつ日々を歩む中で、その生き方から、何か「世」とは違うと感じられ、「それを知りたい」と、教会に導かれる方がおられたら、それは、共に働く聖霊のみ業です。
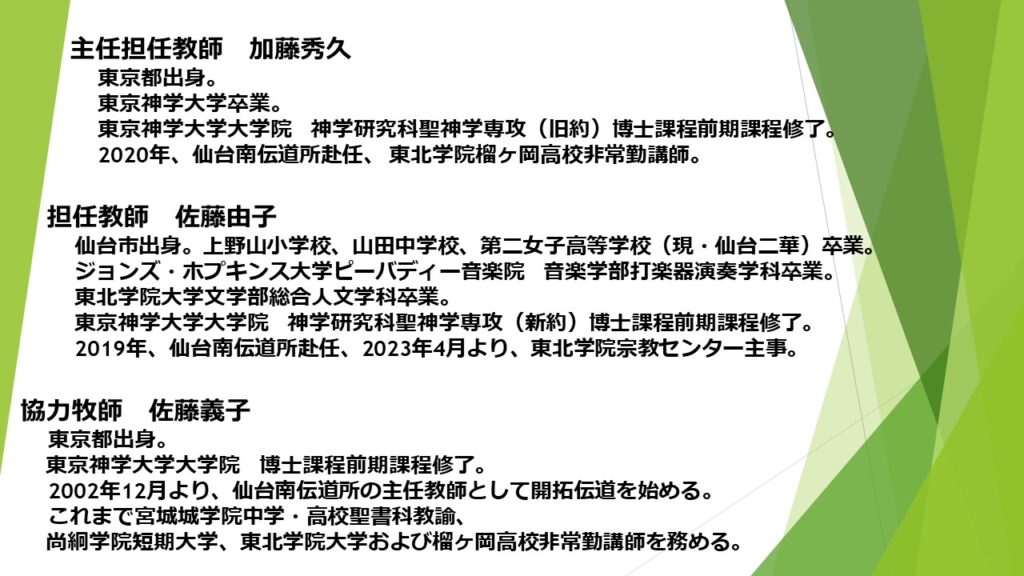
月曜日・火曜日
ユダとイスラエルに対する預言
1: 1~ 11:17 悔い改めの呼びかけ
11:18~ 20:18 エレミヤの苦闘
21: 1~ 24:10 王と預言者に対する預言
水曜日
25: 1~ 25:14 諸国民に対する預言Ⅰ
26: 1~ 29:32 エレミヤの苦難Ⅰ
木曜日
30: 1~ 33:26 慰めの希望の預言
34: 1~ 39:18 エレミヤの苦難Ⅱ
金曜日
40: 1~ 45: 5 エルサレムの陥落以後
46: 1~ 51:64 諸国民に対する預言Ⅱ
52: 1~ 52:34 エルサレムとダビデ王朝の最後
【エレミヤ書について】
エレミヤが預言者として神の召命を受けたのは、ヨシヤ王の治世の第13年(紀元前627年)とされ、エレミヤは18歳、ヨシヤ王は21歳であったと考えられています。
ヨシヤ王は8歳で王位に着いたと記され〈列王記下22:1〉、その治世は前640年からエジプト王ネコとメギドでの戦いで戦死〈列王記下23:29-30〉するまでの31年間です。ヨシヤ王の死は、ユダの自立への希望の終焉を意味し、ユダ王国にはエジプトから重い貢税が課せられました。その後ユダ王国は、バビロンの支配下に置かれ、宗教混合が起こるなど様々な問題に直面しますが、最終的には、エルサレムは包囲され、占領されて、ユダ王国は前587年に滅亡したとされています。
預言者エレミヤは、主の神殿であるエルサレム神殿は、決してユダ王国の安全を保証するものではなく、主の神殿が堕落すれば、主によって、それは破壊されるのだと警告していました。エレミヤの第1回のバビロン捕囚となった人々に送った手紙には、バビロンという異教の支配下にあっても、落ち着いて生活し、ユダ王国を復興させる志を失ってはならないとの励ましの言葉が記されています。
エレミヤは苦難の預言者・涙の預言者として知られていますが、その人生は、決して悲しみに打ちのめされたものではなく、苦難の中でも神の言葉を伝え続ける強さと、主の希望に生きる力は、主を愛し、主に従うことによって与えられることを、私たちに伝えています。
(『ATD20 エレミヤ書』、『旧約聖書略解』エレミヤ書参照。) i
詩編32:1-7 ヨハネ福音書 5:1-18
「起き上がりなさい」 佐藤義子牧師
*はじめに
本日の聖書は、イエス様が祭りの為にエルサレムに来られた時の出来事です。ユダヤの人達が祭りの度ごとにエルサレム神殿での礼拝を守る時、イエス様ご自身も人々と同じように律法に従われて、エルサレムに行かれました(大勢の人達が集まる時を、宣教の機会としても用いられました)。
エルサレム神殿を最初に建てたのは、旧約時代のソロモン王様ですが、その神殿はバビロニア帝国によって破壊され、バビロン捕囚の時代を経て、ペルシャ王によって神殿再建の許可が出され、だいぶ小さくなりましたが、完成の喜びは大きなものでした(エズラ記6:13~、ネヘミヤ記8章参照)。
その後 神殿は、歴史の変遷と共に多くの受難を受けた後、イエス様の時代には、ヘロデ大王が壮大な規模のものに建て直し(ヨハネ福音書2:20)、神殿を含むすべての面積はエルサレムの旧市街の6分の一に当たり、巨大な石垣の名残は、今も、「嘆きの壁」として見ることが出来ます。
このエルサレム神殿から約350メートル北に、「ベトザタ(口語訳聖書はベテスダ)」の池」を囲んで五つの回廊(柱の高さ8,5m、屋根もある)がありました。池から100mほどの所にはローマの軍隊の駐屯地と、総督官邸があり、神殿で何か起こればすぐ駆けつけられるようになっていました。
*横たわる大勢の人々
ベトザタの池を囲んだ回廊には、病気の人、目が見えない人、足の不自由な人、体のマヒした人が大勢横たわっていました。立派な神殿の近くに、大勢の苦しむ人々が集まっていたのは、そこが神殿への通り道で、施しを受けることが出来たという理由の他に、4節(ヨハネ福音書の最後に掲載・212頁)に「彼らは、水が動くのを待っていた。それは、主の使いが時々池に降りてきて、水が動くことがあり、水が動いた時、真っ先に水に入る者は、どんな病気にかかっていても、いやされたからである。」とあります。(ある注解書では、この池が間欠泉で、時々活性を帯びた水の噴出による治癒作用が起こり、最初に入る者は活性の強い水に触れられたと考えています)。
*「良くなりたいか」
イエス様のまなざしは、その中の一人の人に向けられました。彼が38年間病気のために苦しみ、起きて歩くことが出来ないことをイエス様は知り、彼に「良くなりたいか」と声をかけられたのです。
イエス様の問いかけ「良くなりたいか」とは、「あなたは、今ある状態にとどまっていることに満足しているのか。それとも、本当に変えられたいと思っているのか」との、彼の意志の再確認の言葉として聞くことが出来ます。彼の「「治りたい!良くなる時がいつか来る!」との願いは、38年間も空しく待ち続けたために、いつしか無感覚なあきらめの境地に陥っていたことでしょう。良くなりたいと思っても、良くなる時が来るとは実際には考えていなかったでしょう。彼は、誰も自分を助けてくれる人がいない、と絶望的な状況を訴えることしか出来ませんでした。
*わたしたち
カルヴァン(神学者)は、「私達は、この病人と同じことをやっている」と言いました。以下はその説明です。「この人は、自分の考えに従って、神様の助けに枠(わく)を定め、限界づけをして、自分が受け入れられる範囲を超えることは認めない。しかしキリストはその寛大さのゆえに、彼の不完全さを大目に見て下さっている。私達は、自分に近い手段だけにとどまっているのに、キリストは、すべての期待に反して、人知れないところから手をさしのべられ、私たちの信仰のせまさ、小ささをどんなに上回るものであるかを示される。・・だから私達もさまざまな苦悩に責められながら、どんなに長い間どっちつかずの状態に置かれても、時間の長さに嫌気を起こして、勇気を無くしてはならない」。
*「起き上がりなさい」
私達が、あることを願いながら、現実の絶望的な状況を前にして、あきらめ、無気力に陥(おちい)り、祈り求めることをやめようとする時、(あるいはやめた時でさえ)「神様の時」が来るとイエス様の愛のまなざしは私に向けられて「良くなりたいか」と尋ねられ、癒(いや)し主(ぬし)イエス様の権威あるお言葉「起き上がりなさい」との声を今も聞くことが出来ます。
月曜日 1: 1~ 2:23 王妃の交代とモルデカイの働き
火曜日 3: 1~ 4:17 ユダヤ民族絶滅計画とモルデカイの信仰
水曜日 5: 1~ 8: 2 エステルの働きとハマンとモルデカイの逆転
木曜日 8: 3~ 9:19 ユダヤ民族の救いと復讐
金曜日 9:20~10: 3 プリム祭の制定とモルデカイの栄誉
【エステル記について】
聖書の中で、女性の名前が書物のタイトルになっているのは、このエステル記とルツ記の2つだけになります。エステル記はルツ記と同じように、ヘブライ語聖書においては「諸書」に分類され、「メギロート(巻物)」と呼ばれる五つの祭日に朗読される書物の一つです。(雅歌:過越祭、ルツ記:七週祭、哀歌:アブの月の9日・神殿破壊記念日、コヘレト書:仮庵祭、エステル記:プリム祭)
エステル(ヘブル語名は「ハダサ」でミルトスの意)は、ペルシア帝国スサの町(ネヘミヤが滞在していたとされる町)に、捕囚民として住むモルデカイ(ベニヤミン族)の養女として育てられましたが、ユダヤ人でありながら、ペルシア王の王妃としての地位が与えられます。
1章では、なぜエステルが王妃になることができるのかを説明する物語として王妃ワシュティーの退位物語が語られますが、2章からはエステルの歩みと並行して、モルデカイの物語が続きます。異教の地で、主なる神のみを礼拝するユダヤ民族の試練にあって、王や権力に近い場所に置かれた二人が、ユダヤ民族の代表としてどのように行動し、どのように決断していくのかを知ることができる書物です。また同時に、ヨセフ物語やダニエル書にも共通する、主の摂理とご計画、主によって与えられている信仰と知恵が豊かに描かれている書物でもあります。
【プリム(Purim)】
プリムとは、ユダヤ暦においてアダルの月の14日に挙行される春の祝祭である。この祝祭はその聖書的な根拠を与えているエステル記と密接に関連しており、おそらく、ペルシア時代に生じたのであろう。エステルの物語の中で祝われている祝日としてプリムが再現するものは、ユダヤ人のアイデンティティとユダヤ人共同体に対する帝国の脅威、その帝国の脅威に対する勇ましくて巧妙な抵抗、ユダヤ人の驚くべき救出と名誉の回復である。プリム祭は、ユダヤ人の運命を決定した「くじ(ヘブライ語でPur)」を投げることからそう名付けられており、シナゴーグにおけるエステル記の朗読は当然なくてはならぬものとなっている。しかしながら、そのようなことを通り越して、この祝祭は解放されたユダヤ人のアイデンティティと自由を思う存分祝い喜ぶカーニバル気分を誘い、行為で表現する・・・。
比較的後代にユダヤ暦に入れられたこの祝祭は、ペルシア時代にユダヤ教が直面した脅威を映し出しているが、より広い視野で見れば、それはユダヤ人共同体が絶えずさらされていた支配的文化の脅威を映し出している。従ってプリムとは、ユダヤ人のアイデンティティが完全に解放されてもう恐れる必要がなくなった現実を、十分かつ公に明らかにするべく定期的に祝われる祭典であり、ユダヤ人のアイデンティティを抑制し制限し黙らせることを拒絶し、慣習的な政治的要請や社会的期待に服従させられることを拒絶する祭典なのである。(ブルッゲマン、388頁抜粋。)
【エステル記4章から】 「『この時にあたってあなたが口を閉ざしているなら、ユダヤ人の解放と救済は他のところから起こり、あなた自身と父の家は滅ぼされるにちがいない。この時のためにこそ、あなたは王妃の位にまで達したのではないか。』エステルはモルデカイに返事を送った。『・・・私のために三日三晩断食し、飲食を一切断ってください。・・・私は王のもとに参ります。このために死ななければならないのでしたら、死ぬ覚悟でおります。』」
★歴代誌上
月曜日 1: 1~ 9:44 イスラエルの初期の歴史
火曜日 10: 1~29:30 ダビデの治世
★歴代誌下
木曜日 1: 1~ 9:31 ソロモンの統治
金曜日 10: 1~36:23 ユダの歴史
【歴代誌について】
歴代誌は、ヘブライ語聖書では、諸書と呼ばれる部分の最後に置かれ、「日記、年代記」という書名になっています。
申命記史家によって書かれた申命記史書(ヨシュア記・士師記・サムエル記・列王記)に対して、歴代誌史家によって書かれた歴代誌史書がこの歴代誌とエズラ記、ネヘミヤ記と考えられています。
歴代誌はサムエル記と列王記の物語と並行し、王国時代の歴史が書かれています。(マタイ・マルコ・ルカの福音書がそれぞれの視点から同じ物語を書き記しているのと似ています。)歴代誌史書は、申命記史書より後の時代に編集されたと考えられ(前300-前200年頃)、申命記史書にはない記事も記されています。
旧約学者であるM.ノートは、歴代誌史家が特に伝えたかったことは、ダビデの王権と、主を礼拝する祭儀の場所としてのエルサレム神殿の正当性を証明することであると考えました。また、捕囚後にエルサレム神殿を再建し(エズラ記)、そこで礼拝する者達が、「イスラエル」の正統的な後継者であることを証明しようとしているのではないかと考えています(ノート, 353頁)。
(M.ノート『旧約聖書の歴史文学』山我哲雄訳、1988、第2部参照。)
月曜日 1: 1~11:43 ソロモンの統治
火曜日 12: 1~16:34 王国の分裂
水曜日 17: 1~22:53 エリヤの預言の時代
★列王記下
木曜日 1: 1~13:25 エリシャの預言活動
金曜日 14: 1~17:41 エリシャの死からイスラエルの捕囚まで
土曜日 18: 1~25:30 イスラエルの捕囚からユダの捕囚まで
(マクグラス、180-182頁。)
【列王記について】
イスラエルの王国の歴史は、サムエル記上下・列王記上下に記され、七十人訳聖書(LXX)では、王国1,2,3,4と呼ばれています。ダビデとソロモンの時代に、一つの王国として栄えた「イスラエル」でしたが、ソロモンの死後(列王記上12章以降)、「イスラエル」は、「北王国(イスラエル)」と「南王国(ユダ)」に分裂します(BC931-922頃)。そして「北王国(イスラエル)」は、BC722年、「南王国(ユダ)」はBC587に滅亡します。その後、イスラエル(ユダ)の人々は、捕囚民としての生活を強いられますが、帰還が許されたあとに、エルサレム神殿を再建します(BC516-515頃)。しかし、それは「イスラエル」の国の再建ではなく、ペルシア帝国、ローマ帝国の支配下に置かれた「ユダヤ州(属州)」の中で生きる人々の歩みであり、再び「イスラエル」の国が再建されたのは、1948年になってからでした。
列王記は、なぜ「イスラエル」は分裂し、約束の地を失わなければならなかったのか、という問いに答えるようにイスラエルの歴史を語っています。しかし同時に、主は人々を憐れみ続け、預言者を遣わし、神様の言葉を示し、民が主に立ち返り歩む道を備え続けて下さっていることを伝える、希望の書物とも言うことができるのではないでしょうか。